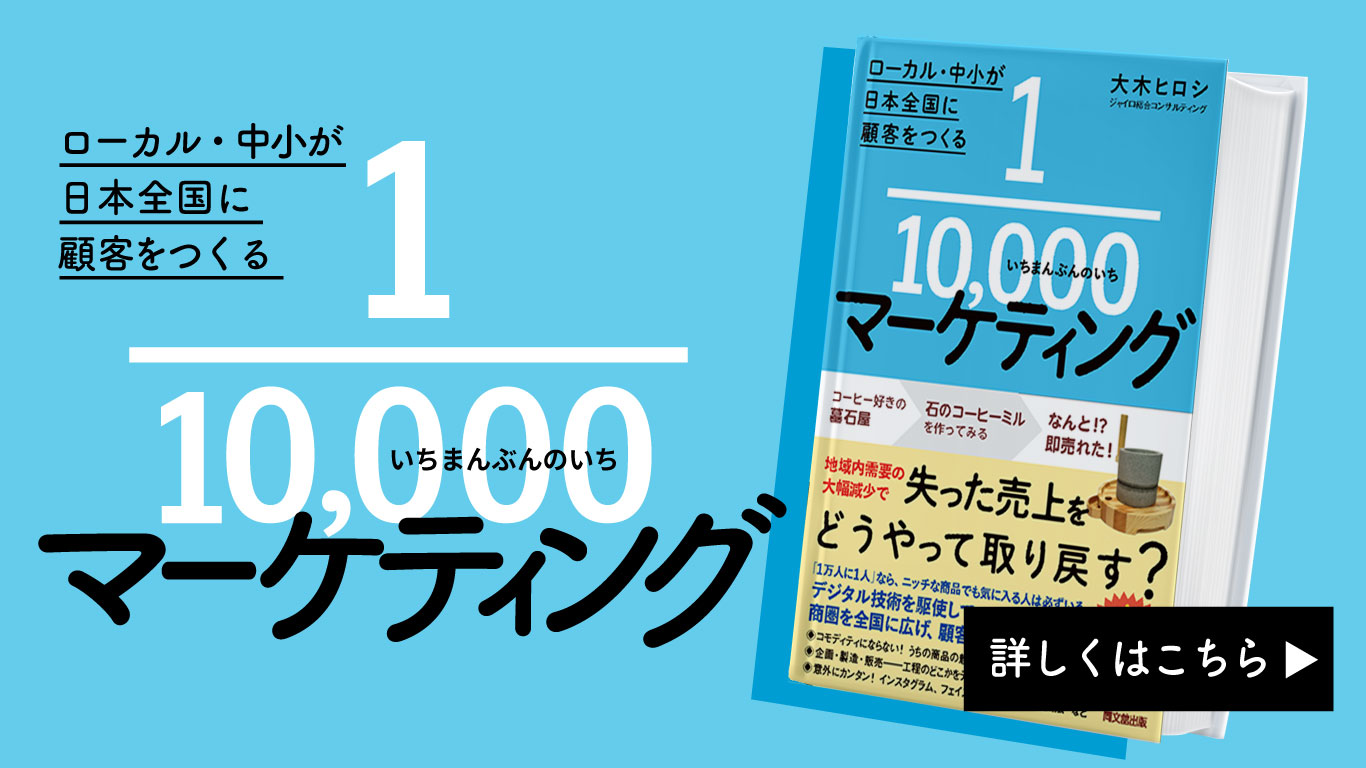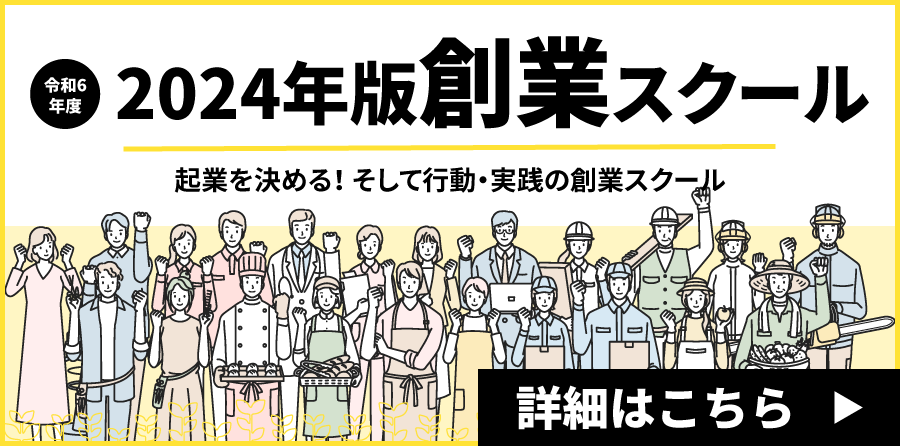インボイス制度対応セミナー【まとめ編】レポート

事業者の皆様は、2023年10月から適用される「インボイス制度」の対策には着手されていますか?「まだ情報収集の段階」「何から手をつけたらいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
今回は、熊本県牛深市・牛深商工会議所の主催で実施した「インボイス制度対応セミナー【まとめ編】」の内容を一部ご紹介します。これからインボイス制度対策を始める方にとって、まずは押さえておきたい情報が満載なので、ぜひ参考にしてください。
研修概要
セミナー名:インボイス制度対応セミナー【まとめ編】
対象:中小・小規模事業者
開催日時:2022年11月4日(金)14:00〜16:00
開催形式:オンライン
講師:松崎哲也
インボイス制度とは?
2023年10月から開始する「適格請求書等保存方式」通称インボイス制度では、消費税の仕入税額控除を適用するために、課税事業者がインボイス(的確請求書)を発行します。
インボイスに記載が必要な事項
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(国税庁「適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-」より引用)
インボイス制度スタート前は、免税事業者(課税売上額が1,000万円以下の事業者)は、売上にかかる消費税を納税する義務はありません。つまり、500万円を売り上げて50万円の消費税が発生する場合、550万円を受け取ることができたわけです。ところがインボイス制度開始後は、これまで免税事業者が利益として得ていた消費税分を誰かが納税する必要があります。
免税事業者から仕入れを行なっている事業者は、これまでは「仕入税額控除」が適用されることでこの消費税を支払う必要がありませんでした。ところが、今後は仕入れ先が免税事業者であった場合、代わりに消費税を納めることとなります。仕入れ先が「課税事業者」であれば、仕入れ額控除が適用されるため、これまで免税事業者との取引は避けられやすくなると予想されます。
こうした背景から、これまで免税事業者として経済活動を行なっていたフリーランスや自営業者に、これまで通り免税事業者として事業を継続するのか、課税事業者として登録をするのがの選択が迫られています。
免税事業者・課税事業者どちらを選ぶか
今回のセミナーでは、冒頭に「免税事業者はやることが4つ、(すでに登録済みの)課税事業者はやることが3つ」と説明がありました。
免税事業者が取り組むこと
- 課税事業者になったときの税額計算
- (課税事業者として登録する場合)登録番号を取得する
- 自社発行の書類のインボイス化
- 他社発行の書類のインボイス確認
課税事業者が取り組むこと
- 登録番号を取得する
- 自社発行の書類のインボイス化
- 他社発行の書類のインボイス確認
適格請求書発行事業者(課税事業者)として登録することは、義務ではありません。これまで通り免税事業者として事業を継続することも可能ですが、取引先に消費税を肩代わりしてもらうため、引き続きパートナーシップを結べるかどうかはお互いの利害や関係性次第となります。
そこで免税事業者は現状を整理し、どちらが自社(自分)にとって有益であるかを検討することが大切です。
免税事業者が検討するべきこと

免税事業者は、昨年度の売上の内訳をもとに自社の販売先を洗い出しましょう。
販売先が事業者のみ、または事業者と一般消費者が混在
このケースは、課税事業者になることを検討する必要があります。
一般消費者のみ
販売先に事業者がいない限り、課税事業者になる必要はありません。
ただし、経費精算のために領収書を求められることが多かったり、法人の利用(接待など)が多い場合は検討の必要があります。
自社の仕入れ先が免税事業者だった場合
自社の仕入れ先が免税事業者であった場合、下に挙げたような方法で自社の利益を守ることが重要です。
- 課税事業者として登録をするよう要請する
- 消費税を支払うことをふまえ、価格交渉を行う
課税事業者としての登録を要請することは、独占禁止法上の違法ではありません。
また仕入れ先が課税事業者かどうかをスマートに聞き出す方法として、自社の適格請求書発行事業者の通知を送付し、書面上で相手方の番号についても問い合わせるという方法があります。
1. 弊社登録番号
T×××××× ××××××
2. 課税事業者のご確認及び登録番号に関するご依頼
課税事業者の場合、貴社の適格請求書発行事業者登録番号を以下の問合せ先まで、ご連絡願います。
また、課税事業者以外(免税事業者等)の場合は、その旨、ご連絡をお願い致します。
もし、適格請求書発行事業者登録番号の取得が未だの場合は、2023年3月31日までに取得願い、2023年5月31日までにご連絡をお願い致します。
3. 問合せ先
部署 氏名
住所
電話番号
メールアドレス
(一般社団法人日本加工食品卸協会「インボイス制度対応―企業間取引の手引き」より引用)
上記の文面を含めた通知書を送ることで、スムーズに登録状況を確認できるでしょう。
登録の注意点
適格請求書発行事業者への登録は、以下の流れで進行します。
- 申請書の提出
- 税務署の審査
- 登録・公表・登録簿の記載
- 登録番号の通知
登録の書式は国税庁のHPから入手できます。制度が開始する2023年10月1日から登録が適用されるためには、2023年3月31日までに申請書類を提出しておく必要があります。また、2023年10月1日を含まない課税期間で申請・登録をした場合は、登録日から2年を経過するまでは免税事業者に戻ることができないので、注意しましょう。
まずはセミナーで情報収集するのがおすすめ
インボイス制度に向けて対策をしたいけれど、どう動くべきかわからない、インターネットで情報収集してみたけれど複雑で理解しがたいという方は、セミナーを利用してみてはいかがでしょうか。ジャイロ総合コンサルティングと商工会議所の提携セミナーではインボイス制度の基礎知識だけではなく、具体的なステップについてもレクチャーしています。
免税事業者として継続するか、課税事業者に切り替えるかの判断に時間を要する場合もあるため、早めに動き始めることをおすすめします。
SNSでセミナーの様子をチェック
#ジャイロのセミナー
開催セミナー
- 【魚津商工会議所主催】「2024年度 ChatGPT入門セミナー」開催のお知らせ
- 【東部商工会産業支援センター主催】「2024年度 ショート動画作成xSNS活用セミナー」開催のお知らせ
- 【矢巾町商工会主催】「2024年度 定額減税セミナー」開催のお知らせ
- 【東京商工会議所 世田谷支部主催】「2024年度 インスタグラム徹底やり直しセミナー」開催のお知らせ
- 【東京商工会議所中野支部主催】「2024年度明日から使えるインバウンド集客と対策法」開催のお知らせ